 |
「書く」といことは本当に難しい。しかもそれが他人に評価される対象ならなおさらです。
大学の入試で小論文が導入されて久しくなりました。そして今では高校、中学入試にも課題としている学校が多くなりました。 保護者の方にとって「作文」はどのように指導していいのか、なかなか頭の痛い教科です。作文とは文字通り文を作る事です。 ではどのように文を作るかと言うと私は最終的には子どもたちの個性、人格であると思います。この作文教室では単にスラスラと文が書けることを目指すのではなく「感動できること」を求めて行っています。 豊かな感性、溢れるような優しさが、良い文を書くための「まずは初めの一歩」だと考えています。 「文はひとなり」 一つひとつの文章、その行間に書き手の「ひととなり」が表れます。 だからこそ、それだからこそ、子どもたちにとって頭だけじゃなくハラハラ、ドキドキの楽しい経験、素敵な思い出、素晴らしい体験を育む事が必要です。 自分の中に思いもかけなかった「自分」を見つけたり、他の人への思いがもっと豊かになるのではないでしょうか。 そして、何よりも、何にもまして 「優しさ」こそが決め手です。 |
| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |
 |
 正確に書く 正確に書く |
 |
最初は「幾つかのもの」を子どもたちに与えます。人形だったり、置物だったり、、、 「さあ、手に取ったものの説明をしてごらん。必ず入れる事はその材質と色、それから初めの出だしは『これは○○です。』と書くように」と指示して書かせます。 いきなり「書け」といわれても、子どもはどのようにして書いていいかわかりません。 書く手はず、考えるきっかけを示す事が必要です。 こちらが導入をしていくと、つられて書き出します。いったん書き始めると子どもの頭は柔らかいから想像の翼は広がり飛び出します。 次のステップは同じように「百科事典で好きな動物を探しなさい」と言って、ある時間内にその動物の事、どこに住んでるか?何を食べるか?などを調べてから、その動物について詳しく書かせます。 この勉強は理科の勉強にもつながります。 また、子どもたちは「絵を書く」ことが好きなので、 できるだけ絵をかく時間を持ちます。 絵を描くことは「対象をより細かく観察する」と云うことに繋がります。 野山に咲く花たちを描くことは(文であっても、絵であっても)感性を磨く事と同時に鋭い観察力を養うためにも必要です。 ぜひ、家で子どもたちと一緒にしてみて下さい。 |
 |
 感じたことをイキイキと描く 感じたことをイキイキと描く |
ここでは「イキイキ」と書くために形容詞や副詞の勉強をします。 たとえば、 「夏」について思い付く言葉を探したり、しりとりをしながら言葉の連想をしたり、「空について5つの表現をする」というようなことを何回も行います。 今まで行ったテーマは以下のようなものです。 1 夏について、、、必ず風の吹く様子を書く 2 好きな動物について、、どこが好きか5つ書く 3 自分の好きな場所を書く 絵も描く 4 反対語を調べて文をつくる 5 同じ意味で別のいい方をさがす 6 日本の昔の行事について調べて書く このようにして、「イキイキと書く」勉強をします。 また、絵本や童話を声に出して読んで、「どういう表現」が好きか、どう思ったかなどを話します。 次に、自分を客観的に見るために家族のことについて書きます。家の中の様子が詳しく述べられていて、つい笑ってしまいます。 当時小学校4年生の男の子の文章を下に載せます。(プライバシーの関係上、こちらで少し編集しました) 豊かな表現力、子どもらしい感性が描かれています。 「僕の家族 僕はお母さんが大好きです。お母さんは僕が勉強していると機嫌がいいです。でも、やらないとすぐに怒ります。妹はキッチリしています。でも、僕がお母さんに怒られると、お母さんの味方をするので憎たらしいです。お父さんは釣りばかりしています。」 |
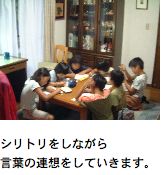 |
 |
 あなたは作家 あなたは作家 |
文字通り自分の好きなように文を作ります。 しかし、「なんでもいいから作れ」といっても難しいので、最初は新聞の4コマ漫画を見て、その前後を自分で想像して書きます。4コマ漫画は起承転結がはっきりしていて、なおかつ笑いを誘うように作られているので教材としては優れています。 ここで面白いのは男女の差がはっきりと出る事です。 男の子はSFのような世界を広げます。 原稿用紙を何枚も使って自分の「世界」を描きます。 冒険が大好きで、自分が主人公になりアニメのように楽しい文を書きます。 一方、女の子は「友情」が多いようです。 仲良しが一度ケンカして、そのあと仲直りして、成長していくというホノボノ系が好きなようです。 回が進むとなぜか短歌(?)を作ったり、詩を書いたりして自作に酔っている様子はあどけなくて、可愛いです。 また、女の子では友達と共同で童話を書いたりする子も出てきます。主人公の女の子の名前を決めるのが大変。「あーーでもない。こーでもない、、、」いつできるのですか?おじょうさん。 そして、いよいよ出来上がると、一般に募集している「○○コンテスト」などに挑戦したりと、なかなか頑張ります。共に作り上げるという作業そのものが楽しいのでしょうね。 どの子にとっても「自分が主人公」と言うのはワクワクするものです。 |
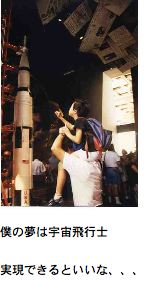 |
 |
 ディベート ディベート |
ここでは自分の考えを相手に伝え説得、納得するということをテーマにグループに分かれてディベートを行います。 今までに行ったテーマは 「田舎がいいか」「都会がいいか」 「言葉は統一している方がいいか,違う方がいいか」 これらに先立ちテーマに付いては、あらかじめ家で調べておきます。 「田舎とは?」「町とは?」、、、童話を調べてきた子もいます。また言葉については簡単な英語の単語を勉強してきた子もいます。 いよいよ本番。 審査員(これも子どもたち)を真ん中に二手に分かれて、それぞれの主張を行います。 初めは冷静に話しているつもりでも、白熱のあまり喧嘩寸前。わかってもらえなくて泣き出す子もいます。 なんとか自分の説が正しいこと、みんなに賛成してもらえるように伝えようと必死です。手ふり、足振り(?) みんななかなかの弁士です。 |
 |
 読書感想文 読書感想文 |
読書感想文は夏休みの課題として与えられることが多くて子どもたちにとっては頭の痛い課題です。 たいては、あらすじを書いて「面白かった」でまとめあげる感想文が多いです。 しかし、感想文を読む人は別にあらすじを知りたくてその文をよ読むわけでは有りません。 「どう思ったか」「どう感じたか」その人だけの文章を読みたいのです。 ではどのようにしたらいいか。 まず、感想文を書く本をザッーと読みます。 ↓ 次にメモをとり、表を作りながら読みます。 たとえば、好きな登場人物、嫌いな人、好きな言葉、いやな表現、感動した所、考えさせられた所、、、などなどです。 こうする中であたまは随分と整理されます。 ↓ メモや表を見ながら自分で優先順位をつけて、一番書きたい事、二番目の事などを決めます。 ↓ そのあとは大体の構図を決めることです。 そのとき大切なことはバランスを考えることです。 全体の1/3に「その本を選んだ理由」と本当に簡単な「あらすじ」を書きます。 次の1/3は自分の決めたテーマについてちょっと詳しく、本の引用なども使って書きます。 そして最後の1/3で自分の感想、考えを述べます。そのとき、「面白かった」で終わるのではなく。読み終えた後の自分の成長を必ず書いておくといいです。 そういう操作を何回かしているうちに、いつのまにか 本を読む時、キチンと整理して読み進む事ができるようになります。 |
 |
 |
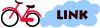 |
 作文が好きになるblog 作文が好きになるblog |
作文教育の課題を多方面から分析しているweblog。 現役先生の豊かな経験と、やさしい視点から子どもたちと保護者に語ってくれます。 また、メールマガジンも発信しています。 |
 実践作文研究 実践作文研究 |
作文指導の情報交流のホームページ。日本一整備された作文サイトをめざしています。メールマガジンも発信。 エネルギー一杯のページです。 |
 |
|

